用語小辞典
能動輸送 active transport
生物は化学的あるいは電気化学的こう配に逆らって物質を輸送する機構を有しており,この代謝的エネルギーに依存した輸送過程を,能動輸送と呼ぶ。
細胞膜や細胞内小器官膜はそれぞれの生理機能に対応する内部のイオン環境を維持している。これらのイオン不均一分布には能動輸送過程が関与している。
能動輸送は他のエネルギーの供与があって初めて可能となる。したがって逆にエネルギー代謝を阻害すると,能動輸送もまた停止してしまう。
アデノシン‐5’‐三リン酸 adenosine‐5’‐triphosphate
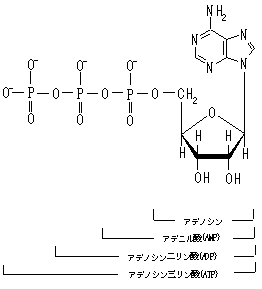
ATP と略称。 C. H. フィスケとY. サバロウ,および K. ローマンにより1929年に,筋肉および肝臓中に存在する熱に不安定なリン酸化合物として発見された。加水分解反応 ATP+H2O → ADP+H3PO4 の pH 7 における標準自由エネルギー変化 ( -DG0‘ ) は 7.3 kcal/mol で,代表的な高エネルギーリン酸化合物である。
生体内においては,発酵,解糖の過程で形成される高エネルギーリン酸化合物からのリン酸基転移反応および酸化的リン酸化反応,光合成生物の光リン酸化反応による ADP ( アデノシン‐5’‐二リン酸 ) のリン酸化によって生成する。
すべての種類の細胞中に存在し,生物のエネルギー代謝において最も中心的な役割を果たす重要な化合物である。
生物は,摂取した栄養物の一部を酸化的に分解することによって,その活動に必要なエネルギーを得る。
一般に,物質が酸化される際にはエネルギーは熱として放出されるが,生物は熱エネルギーを直接に利用することはできない。生体内における ATP の形成は,このエネルギーを熱として散逸させることなく,生化学的諸反応に利用しやすい形に変換する反応である。
形成された ATP は多くの代謝反応に関与し,エネルギー供与体として機能する。生体内で行われる機械的仕事のエネルギー源となるのは ATP である。
アドレナリン adrenaline
アドレナリンは細胞膜にある受容体 ( a と b があり,それぞれ a 1,a 2,b1,b2に分けられる ) を介して作用する。
- 循環器への作用 b1 受容体を介して心筋収縮力を強め,心拍出量を増大し,心筋の興奮性を増す。血管に対しては b2 受容体を介して作用し,皮膚,粘膜,内臓領域の小動脈を収縮させ,骨格筋,肝臓,心臓の血管では拡張作用をもつ。
- 平滑筋への作用 b2 受容体を介して気管支平滑筋を弛緩させる。それによって気管支は拡張し,呼吸量は増大する。その他の平滑筋への作用としては,消化管平滑筋を弛緩させて消化管運動を抑制するなどがある。
- 代謝への作用 肝臓,筋肉のグリコーゲンを分解して血中にブドウ糖を送り出して血糖を上昇させ,脂肪細胞に作用して脂肪を分解し,血中遊離脂肪酸の濃度を上昇させる。また酸素消費量も増加させる。
アルキル化 alkylation
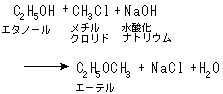
一般には有機化合物に,置換反応あるいは付加反応によってアルキル基( メチル基もその 1 つ )を導入する反応をいう。 簡単な例としてメチル基を導入するアルキル化反応の例を以下に示す。
例:エタノールの酸素原子がアルキル化され,エーテルが生成される( 右図 )。
アロステリック効果 allosteric effect
物質生合成系の初発段階に位置する特定の酵素の活性が,その系の最終生成物によるフィードバック阻害を受けることがある。フィードバック阻害は,酵素合成の抑制とは本質的に異なり,特定の酵素分子と特定の最初生成物との特異的相互作用に由来している。
J. モノーがこのような現象に,基質とは構造が異なる物質による活性の調節という意味で,アロステリック効果という名を与えた。
アンギオテンシン angiotensin
血管収縮などの作用をもつ ポリペプチド。アンギオテンシン I,II,III の 3 種が知られる。
アンギオテンシン I は 10 個のアミノ酸からなり,肝臓で産生される糖タンパク質のアンギオテンシジンに レニン が作用してつくられる。次いでアンギオテンシン I は主として肺にある変換酵素で加水分解され,9 個のアミノ酸からなるアンギオテンシン II に,さらにアンギオテンシナーゼによって,アミノ酸 8 個のアンギオテンシン III に分解される。
これらのうち,最も強い生物活性をもつのはアンギオテンシン II で,血管収縮作用によって血圧を上昇させ,血圧を維持するとともに,アルドステロンの合成を促進させ,腎臓でのナトリウムイオン Na+ の再吸収を促して尿量を減少させ,体液の調節を行う。
アンギオテンシンは不安定な物質で,血中半減時間は 1 分内外にすぎないが,その濃度はレニンによって調節されている。このレニンとアンギオテンシンによってアルドステロンの分泌が調節されているところから,この調節系はレニン‐アンギオテンシン系と呼ばれる。
抗体 antibody
生体にウイルス,細菌,その他の細胞や動植物の成分などの 抗原 が侵入すると,生体の免疫系が刺激され,やがてそれらの侵入物に特異的に結合できるタンパク質が合成されて,細胞表面,血清その他の体液中に出現する。このタンパク質が 抗体 である。
抗原 antigen
抗体 をつくるきっかけとなり,それと反応する物質。物質がもつ抗原としての性質は抗原性と呼ばれ,その能力の強弱は抗原性が高 ( 強 ) い,低 ( 弱 ) い等という。
自己免疫疾患 autoimmune disease
免疫系の反応性に異常があり,本来免疫反応を起こさない自己抗原に対して抗体 ( 自己抗体 ) をつくり,この自己抗原と自己抗体が結合してできる免疫複合体がアレルギー反応を起こし,病変を生ずると考えられている。
自己抗原としては,DNA のほか核成分が重視されている。したがって,自己免疫疾患,自己アレルギー性疾患,免疫複合体病,また関節痛をもつことからリウマチ性疾患の一つと考えられている。
概日リズム circadian rhythm
生物の活動は 1 日を通じさまざまな変動を示す。動物では昼行性あるいは夜行性といわれるような明瞭な日周性が広く知られている ( と呼ばれる ) 。
自然光下で見られる 24 時間周期の日周リズムは多くの場合,生物の内的な概日リズムが外界の光や,温度周期と同調したものである。
概日リズムは単細胞生物以上の動植物に広く見られ,その現れる現象も前記以外に単細胞生物の発光,走光性,細胞分裂,昆虫の羽化,脊椎動物の体内のホルモン分泌など種々の機能に見つかっている。
クラミジア・トラコマチス chlamydia trachomatis
最も一般的な sexually-transmitted disease ( STD ) の病原体のひとつ。女性では,骨盤内炎症性疾患の原因となる。
また,子宮や卵管に瘢痕を残すので,不妊症の原因ともなる。妊娠中の女性を介して,新生児に感染することも知られている。
アジア,アフリカ,中東の砂漠地帯では数百万人の人々がトラコーマによって盲目となっている。トラコーマはこの病原体のある系統によって発症する。
染色体異常 chromosomal aberration
染色体の数や構造に異常が生じることをいう。
減数分裂から受精が完成するまでの間に最も起こりやすい。数の変異には,倍数性,半数性,異数性(基本数の整数倍から外れた染色体数をもつ場合をいう)がある。
一方,構造の変異には,同一染色体内で起こる欠失,重複,逆位,転位などと,他の染色体との間で起こる転座,付着,挿入などがある。
コラーゲン collagen
硬タンパク質の一種で無脊椎,脊椎動物をとわず多細胞動物に広く分布し,量的にも最も多く見いだされるタンパク質である。
哺乳類では全タンパク質の約 1/4 をしめる。動物の結合組織を構築している主要な繊維状要素。張力に対してたいへん強いので,腱や靭帯で力を損失することなく伝達するのにつごうがよい。
熱湯処理で徐々に溶けて水に可溶性のゼラチンに変わる。
動物の成長とともに分子間に橋かけ構造が生じ不溶性になる。コラーゲンの基本的な構造単位は分子量約 30 万のトロポコラーゲンである。この分子は3本のペプチド鎖から成り,それらがより合わさって3本鎖右巻き超らせんを構成している。
トロポコラーゲン分子が会合してコラーゲン繊維 ( 膠原繊維 ) を形成するが,各分子は軸方向に 1/4 ずつずれて配列し,その結果 640Å 間隔の独特の縞模様を形成する。アミノ酸組成はグリシン,プロリン,ハイドロキシプロリンが多く,含硫アミノ酸が少ない。
補酵素 coenzyme
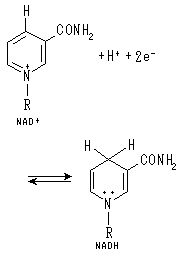
助酵素,コエンザイムとも呼ばれる。酵素の活性発現のためには,タンパク質以外の分子が,可逆的にタンパク質成分に結合することが必要条件とされるものが少なくない。それらの分子を補欠分子族 prosthetic group,または配合団と呼ぶが,金属原子,各種の無機アニオン,カチオンなどを除き,有機分子として作用するものを補酵素と呼ぶ。
補酵素を解離させた残りのタンパク質部分をアポ酵素 apoenzyme,アポ酵素に補酵素が結合したものをホロ酵素 holoenzyme と呼ぶ。代表的補酵素について以下に述べる。
(例) ニコチン酸の誘導体 NAD+ ( ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド ),NADP+ ( ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 ),および両者の還元型である NADH と NADPH は生物界に広く分布し,乳酸脱水素酵素反応をはじめ,各種の酸化還元反応に関与する酵素の補酵素となる。
NAD+の還元は右式のように立体特異的な反応として進行するが,この種のビタミンの欠乏は ペラグラ pellagra の原因となる。
膠原繊維 collagen fiber
結合組織の細胞間に存在する最も普通の繊維である。真皮,腱,靭帯などはこの繊維の集束である。骨の細胞間質としても見られる。
その成分は コラーゲン で,これはグリシン,プロリン,ヒドロキシプロリンを豊富に含む。1本の膠原繊維は膠原原繊維と呼ばれる無数の細い繊維の集まりであり,これはさらに細い幅 500 – 1000Å の膠原細繊維の集まりからなる。
膠原細繊維を電子顕微鏡で見ると640Åを間隔とする横紋がみられる。膠原細繊維は径14Å,長さ2600Åのトロポコラーゲンと呼ばれる棒状のタンパク質分子がその長さの 1/4 ずつ交互にずれながら横に並んで束を形成したもので,640Å の横紋はそのために作られる。
トロポコラーゲンは繊維芽細胞によって作られ,細胞体外へ出されてから重合し,膠原細繊維となる。膠原繊維はヘマトキシリン・エオジン染色ではエオジンによって赤色に染まり,またアニリンやライト緑によく染まる。
偏光顕微鏡で見ると複屈折を示す。これはトロポコラーゲン分子が方向性をもって配列しているからである。この繊維の特性は引張りに対して強いことで,5 kg/mm2 の引張りに耐える。
共有結合 covalent bond
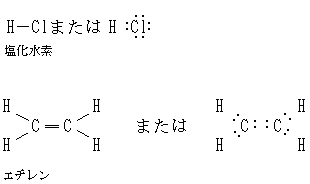
電子対結合ともいう。化学結合の代表的な様式の一つで,原子と原子の間に形式的に最外殻の電子が1~3組の電子対をつくっているとみなされ,しかもその電子がどちらの原子に所属するともいえず,むしろ両原子に(さらに分子内の他の原子にまで)共有されているとみなされる結合。
たとえば塩化水素 HCl,エチレン C2H4の場合は,図のように表記する。
共有結合は大部分の有機化合物の結合様式であるが,無機化合物にも例は多く,ダイヤモンド,シリコン,グラファイト等も典型的な共有結合の例である。
サイトカイン cytokine
マクロファージまたはリンパ球が抗体刺激を受けて傍分泌(パラクリン)分泌 〔自己(オートクリン)分泌の例もある〕 される糖タンパク質。種々のリンフォカイン lymphokine, ケモカイン chemokine,インターフェロン interferon,コロニー刺激因子 colony-stimulating factor,ならびに腫瘍壊死因子 tumor necrosis factor がその例である。
エラスチン elastin
硬タンパク質の 1 種で,構成するアミノ酸の 80 – 90% はロイシン,アラニン,グリシン,プロリン,バリンの 5 種からなる。
血管壁や靭帯等に多く含まれていて,これらの組織の弾性的性質はエラスチンの特性によるが,この弾力性はエラスチン中のデスモシン desmocine という特殊なアミノ酸の存在に基づく。
弱酸,弱アルカリなどの化学的処理に対して安定であるが,エラスターゼをはじめとするタンパク分解酵素によってゆるやかに分解される。
エンハンサー enhancer
DNA 上の転写開始を促進する部位。エンハンサーがプロモーターと異なる点は,それらが影響する遺伝子からかなり離れていることである(上流,5′ 末端側あるいは下流,3′ 末端側)。
大腸菌 Escherichia coli
腸内細菌科の大腸菌属 Escherichia の1種。グラム陰性で,通性嫌気性の杆菌。
長さ2 – 4 mm,幅 0.4 – 0.7 mm。周在性の鞭毛をもち,運動性を有する。ヒトを含む動物の腸管とくに大腸内を生息の場所とするが,糞便に汚染された外界にも広く存在する。
大腸菌は健康人の腸管に常在しており,それらは無害な寄生菌であるが,人体の常在部以外の臓器に侵入した場合には,病原性を発揮し,感染症を引き起こすことがある。最も多いのは尿路感染症である。
これらのもの以外に大腸菌の一部には,病原大腸菌と呼ばれる群があり,下痢や腸炎を引き起こす。病原大腸菌には,腸管侵襲性,腸管毒素原性,腸管病原性大腸菌,腸管出血性大腸菌の4種類のものが知られている。
また近年,食中毒事例が目立ってきている病原大腸菌 O-157 は,ベロ毒素と呼ばれる赤痢菌様毒素を産生する腸管出血性大腸菌である。
大腸菌は遺伝学的・生化学的研究材料,および近年ではバイオテクノロジーの研究材料として最も頻繁に用いられている。
ガングリオシド ganglioside
シアル酸を有する糖脂質はとくにガングリオシド ganglioside とよばれる。シアル酸は糖タンパク質,糖脂質の非還元末端にしばしば存在する。細胞膜は糖タンパク質,糖脂質に富み,この糖部分は細胞膜の表層側に位置している。
したがって,シアル酸は細胞表層の負電荷のかなりの部分を担うことになる。実際,赤血球の電気泳動移動度は,シアル酸を酵素によって除去すると大きく低下する。
ゲノム genome
本来の定義では,1 個の配偶子に存在する染色体の 1 組,ないしはこの 1 組の染色体に含まれる遺伝子全体をさす ( ウィンクラー H. Winkler,1920 ) 。
しかし今日ではこの定義が拡大されて,それぞれの遺伝子をひとそろい含んでいるバクテリア,ウイルス,プラスミド,ミトコンドリアあるいは葉緑体の DNA や RNA の単一分子をもゲノムとよぶようになってきている。
[ 主な生物のゲノム・サイズについてはこちらを参照のこと ]
遺伝子型 genotype
接合体や配偶子の遺伝子構成を 遺伝子型 genotype という。これに対し,接合体の表に現れる形質を 表現型 phenotype とよぶ。接合体において 2 つの対立遺伝子が同一のときは ホモ接合体 homozygote,異なるときは ヘテロ接合体 heterozygote という。
グルカゴン glucagon
ペプチドホルモンの一つで,肝臓に作用しグリコーゲンを分解して血液中の糖分 ( ブドウ糖 ) を上昇させる。またアミノ酸からの糖新生や脂肪組織における脂肪分解を促進する。
これらの作用は,グルカゴンが標的器官 ( 肝臓,脂肪組織など ) の細胞膜上に存在する特異的受容体 ( レセプター ) と結合して,細胞内サイクリック AMP 産生を増加させることによる。
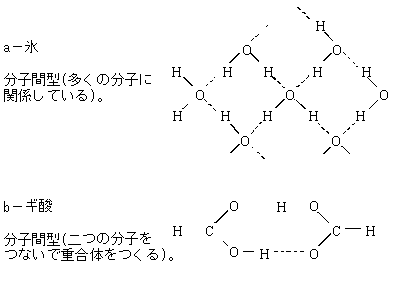
グルカゴンは膵臓のランゲルハンス島にある A ( a,a2 ) 細胞で合成,分泌されるが,このアミノ酸 29 個からなる分子量約 3,500 の膵グルカゴンのほかに,より分子量の大きいいくつかの膵外グルカゴンも腸管などで見いだされている。。
水素結合 hydrogen bond
化学結合の一種。水素原子は原子核 ( 陽子 ) のまわりに 1 個の電子しかなく,他の電気陰性度の大きい原子( 窒素 N,酸素 O,フッ素 F など )との化学結合にその電子を使うと,その電子は相手原子に引き寄せられ,自身は陽に帯電した裸の原子核だけになりやすい。
また近くに陰性の強い別の原子があると,これと引き合って弱いながらも結合をつくるようになる。
このような結合を水素結合という。普通の共有結合に比べて強さは 1/10 くらいであるが,固体や液体の中で分子相互の配向を決める程度の結合力である。
ヒト白血球抗原 human leucocyte antigen,HLA
ヒトの第 6 染色体上に HLA 抗原の決定因子があり,A,B,C,D の 4 つの遺伝子座と D と関係のある DP,DQ,DR が明らかになっている。
HLA 型は現在では,全部で約130種類が明らかにされている。
臓器移植の際に,ドナーとレシピエントの適合性を調べること組織適合性試験と呼ぶ。組織適合性が 100% 一致するのは,一卵性双子間の移植であるが,通常はこのような一致は望めないので,よりよい組合せを探すことが目的となる。
腎臓移植の成績と HLA 型適合度の関係をみると,血縁者間の移植では,とくに密接な関係が認められている。しかし,心移植,肝移植では HLA の違いは予後にあまり関係ないといわれている。
ヒト免疫不全ウイルス HIV
ヒト免疫不全ウイルス human immunodeficiensy virus (HIV) の感染により,後天性免疫不全症候群( acquired immuno deficiency syndorome,AIDS )が発症する。エイズウイルスとも呼ばれる。
細胞性免疫不全により,日和見感染症,カポジ肉腫,リンパ腫などが引き起こされる。エイズウイルスは RNA ウイルスで,HTLV とともにレトロウイルスと呼ばれる RNA ウイルスの仲間である。
相同染色体 homologous chromosome と対立遺伝子 alleles
核には決まった数の染色体があり,1 つ 1 つの核内遺伝子 ( 以下,遺伝子という ) はいずれか 1 本の染色体の一定の部分を占めている。いいかえれば,遺伝子が線状に配列したものが染色体である。
雌雄の配偶子の合体によってできた接合体には,種類の同じ染色体,すなわちそれを構成している遺伝子の種類と配列順序がまったく等しい染色体が対になっている。このような染色体を 相同染色体 という。これに対し,構成遺伝子の種類がまったく異なる染色体を非相同染色体という。
対をなす相同染色体の一方は父親から,他方は母親からきたものである。雌雄の性には関係なく,すべての接合体に対で存在する染色体を常染色体という。当然ながら,常染色体に含まれる遺伝子も対をなしている。この相同染色体上に対をなしている遺伝子を 対立遺伝子 alleles とよぶ。
常染色体上の遺伝子で支配される形質は両親からきた 2 つの対立遺伝子の支配下にあり,その遺伝は常染色体遺伝とよばれる。これに対し,性染色体上の遺伝子で支配される形質は伴性遺伝をする。常染色体や性染色体上の遺伝子とその支配形質はメンデルの法則に従い遺伝する。
インプリンティング(刷込み) imprinting
一部の動物が誕生直後に経験した特別な対象に対して示す特殊なタイプの学習。ローレンツは,ハイイロガンの雛が孵化後,初めて出会った動く対象に対して,それが母鳥であれ人間であれ,あるいは一輪車でさえ,後を追って行くことを発見した。刷込みには次のような一般的特徴をもつ:
- 学習の成立は出生後のある一定の短い期間 ( 感受期 sensitive period または 臨界期 critical period ) に限られる。たとえば,誕生後しばらく仲間から離しておいた雛は,感受期をすぎて戻してももはや仲間となじめず,交配もうまくいかない。
- いったん刷り込まれると,きわめて安定である。たとえば,人間に刷り込まれた後,母親に引き合わせても,人間に対する刷込みは消えない。
- 早い時期に完了した刷込みがずっと後の行動に影響を与えることがある。たとえば,人間の男性に刷り込まれた雛が,繁殖期に人間の女性を性行動の対象とする。
刷込み現象は,最初鳥類で見つかったものであるが,現在ではモルモットや早成性の有蹄類など哺乳類でも見られることが報告されている。
刷込みの機能は,親と子,兄弟姉妹間の親密感を増し,きずなを強めることで安全を図ることにあると考えられるが ( なぜなら,自然状態では,最初に出会う動く物体は,ほとんどの場合親か兄弟姉妹であるから ),最近では親子の親密感によって近親交配を防ぐ二次的な機能をもつのではないかという説も出されている。
インスリン insulin
インスリンは,膵臓に存在するランゲルハンス島(膵島)のβ細胞から分泌されるペプチドホルモンの一種である。
私たちが生きていくためにはエネルギーが必要で,エネルギーは食べることで得られるブドウ糖によって作られる。しかし,ブドウ糖は単独ではエネルギーにならない。すい臓から分泌される「インスリン」というホルモンの働きかけによって細胞の中へ取り込まれ,初めてエネルギーとして利用したり、貯蔵したり出来る。
インスリンは食事によって上昇した血糖に応じて,すい臓から分泌され,肝臓へと運ばれてブドウ糖を細胞の中へ取り込む働きをしている。インスリンがブドウ糖の使い道をうまくコントロールしているので、一時的に上昇した血糖も数時間後には食前の値まで下がる。
インスリンは体内で唯一血糖を下げることの出来る大切なホルモンである。
エリテマトーデス lupus erythematodes
膠原病 ( こうげんびよう ) に属する疾患で,その代表的なものと考えられている。10 – 20 歳代の女性に多く,男性にはまれである。症状として特徴的紅斑が皮膚表面に出るために,エリテマトーデス(紅斑症,紅斑性狼瘡 ( ろうそう ) といわれている。
全身的に多臓器の病変を示す全身性エリテマトーデス systemic lupus erythematodes ( SLE と略される ) と,病変が皮膚に限られる円板状エリテマトーデス discoid lupus erythematodes ( DLE と略される ) との二つが区別されている。
リンパ球 lymphocyte
免疫過程において重要な役割をはたす。脊椎動物では,胸腺由来の T 細胞 thymus derived cell ( T リンパ球 ),および鳥類のファブリキウス嚢 bursa fabricii ないし骨髄 bone marrow 由来の B 細胞 (B リンパ球) に大別される。B 細胞表面には抗体分子のレセプターがあり,これで抗原を認識して,T 細胞の関与のもとで,大量に抗体を産生する形質細胞へと分化する。T 細胞からはインターロイキン 4,5,6 が産生され,これらのタンパク質によって,B 細胞の増殖や形質細胞への分化が誘導される。
T 細胞は胸腺から全身に送られ,B 細胞の増殖分化を促したり,その抗体産生を刺激したり抑制したり,マクロファージの機能を刺激したり,異種細胞を障害したりするなど多様の能力をもつ。マクロファージ macrophage ( 大食細胞 ) は他の器官の大食細胞と同様に異物や細菌などをたべて処理する。
マトリクス ( 基質 ) matrix
細胞外液の一部で,血漿と同様,種々の栄養物,電解質,ホルモン等を含む液体で細胞を直接とりまき,細胞の生活環境を形成しているもの。
血漿( 管内細胞外液 )とともに生体内の内部環境を形成し,その電解質組成,浸透圧,pH は血漿とつねに平衡しており,かつ恒常的に至適な状態に保たれている。
メラニン細胞刺激ホルモン melanocyte‐stimulating hormone
MSH と略す。動物の脳下垂体から,α,β および γ の 3 種類の MSH が分離されている。α‐MSH は,下等脊椎動物で色素沈着作用をもつホルモンとして早くから知られているホルモンで,13 個のアミノ酸からなり,その配列は ACTH の N 末端 1 – 13 に一致する。
ただ,ヒトの成人では α‐MSH は存在しない。これまでヒトにおいてメラニン細胞刺激作用をもつホルモンとして β‐MSH ( アミノ酸 22 個 ) が提唱されてきたが,最近の検討によれば,この物質は抽出操作中にβ‐リポトロピンから生じた人工産物であることが判明した。
したがって,ヒトの場合には,メラニン細胞刺激作用をもつホルモンは β‐リポトロピンと ACTH である。γ‐MSH は,最近 ACTH と β‐リポトロピンの共通前駆体の一部を構成するホルモンとして発見されたが,まだそのホルモンとしての役割は明らかにされていない。
マイコプラズマ mycoplasma
マイコプラズマ目 Mycoplasmatales に属する細菌の総称。マイコプラズマ属をはじめ 3 属が分類されている。
菌体は径 125 – 200 nm の基本小体と,ときに長さが 150 mm にもなるフィラメントからなる。最小の生物として知られ,電子顕微鏡でしか見ることができない。
菌体の大きさがウイルスなみであることや,細胞壁を欠くことなどから,細菌とウイルスの中間に位置するものと考えられるが,基本小体が増殖能をもち,無細胞培地で培養できることから,現在では細菌に分類されている。
神経筋接合部 neuromuscular junction ( NMJ )
運動神経繊維が筋繊維と接合する部分をいう。
脊椎動物の骨格筋では,この部分を終板 end‐plate ともいう。運動神経繊維の末端は髄比がなくなり,枝分れして筋繊維表面の細胞膜と約 500Å の距離で相対している。
この部分の筋細胞膜には多数のひだがある。神経筋接合部はシナプスの一種とみなすことができ,運動神経繊維のインパルスはここを通過して筋繊維に伝えられるが,筋繊維のインパルスが神経繊維に伝わることはない。
これは,神経筋接合部における興奮の伝達が神経末端からインパルスによって分泌される伝達物質をなかだちとしていることによる。
脊椎動物の終板における伝達物質はアセチルコリンであるが,節足動物の神経筋接合部の伝達物質はグルタミン酸である。神経筋接合部におけるインパルスの伝わりは種々の薬物により阻害される。有名な矢毒であるクラーレもその一つである。
オープン・リーディング・フレーム Open Reading Frame (ORF)
タンパク質が合成される最初の塩基(AUG)から停止コドンまで(イントロン除く)の読み枠を指す。
オルソログ遺伝子 orthologous gene
異なる生物が共通祖先に由来する遺伝子を持つとき,それらの遺伝子はオルソログ(直系遺伝子)と呼ばれる。オルソログは,種分化の過程で生じた,相同な機能をもった遺伝子をいう。
例)ヒトのIGF1とマウスのIGF1 → 「オルソログ」
ヒトのIGF1とヒトのIGF2 → 「パラログ」
オゾン層 ozone layer ( shield )
上空大気中でオゾン量の多い領域。地上高度 20 km ないし 25 km を中心に,厚さ約 20 km にわたり分布する。
オゾンは波長 200 – 300 nm の紫外線を強く吸収するので,生物細胞中の核酸を壊してしまう太陽紫外線放射が地上に侵入するのを防いでくれる。それゆえに,オゾン層は地上生物の生存にとって不可欠の存在である。
オゾン層の紫外線遮へい効果は 300 nm 付近から長波長側では不完全となり,太陽紫外線( 波長域 305 ± 10 nm )がわずかに地上に漏れ出してくる。この紫外線は UV‐B とも呼ばれ,生物機能に損害を与えるが,これに対して地上生物は進化の過程で種々な防御機能を獲得している。
UV‐B の地上照射量はオゾン量の変動に敏感であるから ( 変化率にして約 2 倍の増幅度がある ) ,オゾン量の長期変動は地上生物にとって重要な環境因子である。
パラログ遺伝子 paralogous gene
ある生物がもつ2つの遺伝子が祖先種では同一の遺伝子であった場合,それらの遺伝子はパラログ(側系遺伝子)と呼ばれる。パラログは,進化の過程で遺伝子重複によって生じ,機能の異なる遺伝子になる。側系遺伝子に対して,別の生物のゲノムの中で同じ役割をする相同遺伝子は直系遺伝子(ortholog)とよんで区別する。
例)ヒトのIGF1とヒトのIGF2 → 「パラログ」
ヒトのIGF1とマウスのIGF1 → 「オルソログ」
単為発生 ( 生殖 ) parthenogenesis
有性生殖においては大・小 2 種類の配偶子,すなわち卵と精子が受精することによって発生を開始するが,どちらか一方の配偶子のみで発生が開始する場合がある。そのような発生を単為発生といい,また,単為発生が正常の生殖過程の一部として認められる場合に単為生殖という。雌性配偶子からの単為生殖を処女生殖,雄性配偶子からの単為生殖を童貞生殖と呼ぶこともある。
植物では,半数体の配偶子からの単為生殖の例がシロバナヨウシュチョウセンアサガオなどで知られているが,一般に生じた植物体は全体に小さくて,種子をつくらない。倍数体の配偶子からの単為生殖の例は,ドクダミ,ハンノキ,タンポポなどで知られている。またツチトリモチでは,常習的に単為生殖によって種子がつくられている。
無脊椎動物では,昆虫のミツバチ,アリマキ,タマバエ,甲殻類のミジンコなどの例が古くからよく知られている。ミツバチでは染色体数 2n = 32 の雌と働きバチは受精卵から生じ,n = 16 の半数の単為発生胚は雄になる。アリマキやミジンコでは季節的に単為生殖をして雌のみが生じ,有性生殖世代と交代する。
脊椎動物のような高等動物では単為生殖は行われないと考えられていた時代もあったが,1940 年代から魚類のアマゾンモーリーやアジア大陸北部産のギベリオブナ,日本産のギンブナなどで雌だけのコロニーのあることが見いだされ,雌性単為生殖を行っていることが確認された。ギンブナでは卵がドジョウ精子で媒精された後,発生が開始し,ドジョウ精子由来のゲノムは利用されず,雌のギンブナ個体となることが知られている。
爬虫類では,アルメニアに産するカナヘビ属の 1 種,およびアメリカ,ニューメキシコに産するハシリトカゲ属の 1 種が雌性単為生殖を行うことが知られている。哺乳類で単為生殖を行う種の存在は知られていない。
下等脊椎動物卵では,実験的に未受精卵を刺激して単為発生を行わせ,個体を得ることが可能なものもある ( 例えば,カエルや一部の魚類 )。しかし哺乳類胚では,現在までのところ実験的に単為発生を誘発した胚で初期の体節期以上に発生が進行した確かな例は報告されていない。例外的に,マウス受精卵において,前核の融合が起こる以前に,雌性前核と雄性前核の一方を実験的に除去し,残った前核の染色体を 2 倍化した後発生を継続させて成体に至らしめた報告がある。しかし,この結果は他の実験室で追試することができないまま現在に至っている。
ペラグラ pellagra
ビタミン B 群,とくにニコチン酸アミド欠乏による全身性疾患。皮膚では顔面,手足の背面,上胸部などの露出部に紅斑,水疱,潰瘍を生じ,やがて色素沈着と萎縮を残す。
このほか消化器症状,神経症状を伴い,重症の場合は死亡する。元来は地中海地方で流行していたもので,病名もイタリア語の pelle ( 皮膚の ) + agra ( 痛み症 ) による。その後アメリカにも出現し,現在では世界的にみられる。
日本ではきわめてまれで,常習飲酒者,胃切除者などにみられることがある。食生活改善,欠乏ビタミンの補給と紫外線防護が行われる。古くはトウモロコシが主因とされたことがある。
表現型 phenotype
ある生物のもつ遺伝子型が形質として表現されたものである。 その生物の形態,構造,行動,生理的性質などを含む。獲得形質は含まない。
phiX-174
大腸菌に感染するバクテリオファージで,近年の分子遺伝学の進展に著しく貢献した研究対象の 1 つ。その DNA 単一鎖は 5,386 個の塩基を持っており,10 個の遺伝子をコードする。
光周期 photoperiodism
1 日の明暗サイクルを光周期と呼び,生物が光周期の季節的な変化に反応して物質代謝・発育・生殖・行動などを調節する性質を光周性という。
生物界に広く見られ,環境の季節的な変化にたいする重要な適応機構である。
形質細胞 Plasma Cell
B 細胞が抗原の刺激と T 細胞の補助を受けて増殖分化した最終形のもので、免疫グロブリン(抗体)を生産する細胞。
ポリオウイルス poliovirus
届出伝染病ポリオ ( かつては小児麻痺と称した ) はポリオウイルスによる感染症である。下肢や上肢の永久的な麻痺を起こす疾患として恐れられが,1954 年に J. E. ソークによって不活性ワクチンが,58 年に A. B. セービンによって弱毒ワクチンが開発され,ポリオは著しく減少した。
ポリオウイルスは,RNA ウイルスのピコウイルス属に属する直径 25 nm の球状のウイルスで,血清学的にはI 型 ( ブルンヒルデ型 ) ,II 型 ( ランシング型 ) ,III 型 ( レオン型 ) の 3 型に分類される。このうち I 型が大流行をひき起こすといわれる。
このポリオウイルスが経口感染すると小腸で増殖し,約 1 週間で血液中に入って 12 – 14 日目に中枢神経に侵入する。ウイルスは脊髄の運動神経細胞を破壊し,その障害は不可逆的なので麻痺を残す。しかし感染を受けたもの全部が麻痺を起こすのではなく,約 90% 以上は麻痺が起こらない。
原核生物 prokaryote と真核生物 eukaryote
すべての生物がもつ基本的な情報システムは遺伝子 DNA ( 一部のウイルスは RNA を遺伝物質としている )であるが,
- 原核生物 – 細菌,ラン藻のように初期の生物の姿をとどめていると考えられる生物では,遺伝子 DNA が裸のまま細胞の中に収まっている。
- 真核生物 – すべての動物,植物では,遺伝子DNA は染色体の中に収められ,この染色体の集団が細胞分裂の間期には核膜に包まれて,いわゆる核を形成している。
この違いは,細胞内における遺伝子情報の発現,遺伝子の増殖や組換えなどの様式にも反映して大きな違いを生じている。
procaryote または eucaryote と表記されることもある。
プロモーター promoter
DNA 上の転写開始を指令する部位 ( 通常は遺伝子の 5′ 末端側 )。RNA ポリメラーゼや他の転写調節因子が,プロモーターにまず結合し,DNA の二重鎖を局所的に解離させ,そのうちの 1 本の鎖を鋳型に相補的な RNA を合成する。
プロテオグリカン proteoglycan
タンパク質と多糖の結合した物質で,おもに動物の細胞間組織( 細胞外基質 )の構成成分である。
糖タンパク質と異なるのは,糖タンパク質ではタンパク質の占める割合が高いが,プロテオグリカンでは多糖の比率が高い点である(70% が多糖)。
多糖部分はムコ多糖で,ムコ多糖の名まえの前にプロテオ( タンパク質の意 )を付けて呼ぶ。
- プロテオコンドロイチン硫酸は動物の軟骨などに多く,細胞間組織の主成分である。
- プロテオデルマタン硫酸は,哺乳類の真皮,腱などでコラーゲン繊維とともに存在する。
- プロテオヒアルロン酸は,動物の関節液,眼球の硝子体や結合組織に存在する。
- プロテオヘパラン硫酸は,細胞膜に存在するという点で他のプロテオグリカンとは異なる。
- プロテオケラタン硫酸は,角膜,椎間板,軟骨などに存在し,コンドロイチン硫酸と共存する例が多い。
- ヘパリンもタンパク質と結合してプロテオグリカンを形成するが,他とは違い,細胞内成分として存在する点が特徴である。
レニン renin
主として腎臓の傍糸球体細胞から放出される一種のタンパク質分解酵素で,高血圧の発症あるいは維持に重要な役割を果たすものとして注目されている。
レニンの働きによって血清タンパク質からつくられる アンギオテンシン II にはきわめて強力な血圧上昇作用があり,これが高血圧の発症あるいは維持に関与しているのではないかと考えられている。
生殖的隔離 reproductive isolation
二つの個体群の間での生殖がほとんど行えない状況を指す。生殖的隔離をもたらす機構には様々なものが知られているが、それらを交配前隔離(premating isolation)と交配後隔離(postmating isolation)とに大別し,さらに細かく,接合子の形成がみられるか否かを基準として接合前隔離(prezygotic isolation)と接合後隔離(postzygotic isolation)とに区分することもある。
リボ核酸 ribonucleic acid
RNA と略記。核酸のうち糖成分が D‐リボースであるものをいう。塩基としてはアデニン,グアニン,シトシン,ウラシルの 4 塩基( それぞれ A,G,C,U と略す )が主成分であるが,これらのメチル誘導体などの修飾塩基を微量含むこともある。
DNA 上の遺伝情報に基づいてタンパク質を合成する過程で,種々の重要な役割を果たす。
RNA 依存性 DNA ポリメラーゼ RNA dependent DNA polymerase
逆転写酵素 reverse transcriptase とも呼ばれる。RNA の塩基配列をもとに DNA を合成する酵素で,RNA ウイルスの 1 種類であるレトロウイルス類の粒子内に含まれ,ウイルスの 1 本鎖 RNA を鋳型に,相補的な塩基配列をもつ DNA 鎖を合成する。合成後の RNA と DNA との二重鎖をもとに,二重鎖 DNA を合成する反応もこの酵素が行う。
RNA 腫瘍ウイルスで発見されたことから,この類のウイルスに起因するガン化機構に知見を与えたが,RNA を鋳型に DNA を合成するという,通常とは逆方向の遺伝情報の流れの存在を示した意義も大きい。
遺伝子工学の分野において,この酵素の特異な性質を利用し,mRNA を鋳型に相補的な DNA( cDNA と呼ばれる )を合成することが行われており,遺伝子のクローン化の一手段となっている。
自家不和合性 self‐incompatibility
雌雄同花で正常な機能をもつ雌雄両配偶子が同時に形成されるにもかかわらず,受粉がおこなわれても花粉の不発芽,花粉管の花柱への侵入不能,花粉管の伸長速度低下または停止などにより,自家受精 が妨げられる現象。
この現象は高等植物に広く見いだされ,明らかに 他殖性 allogamy を維持,促進する繁殖様式の一つと考えられている。
不和合性にはめしべやおしべになんら形態的な分化が認められない 同型不和合性 と,めしべとおしべの長さ,柱頭の表面の形態,花粉の大きさや形状などに分化のみられる 異型不和合性 が知られている。
- 同型不和合性の場合は外部形態に差異がないので,交配によってのみ検出でき,一般にこの機構の多くは遺伝子によって制御されている。
- 配偶体不和合性 – 精子と卵細胞の受精後配偶子間の不調和によって発現する( アカバナ科,マメ科,ナス科植物など )
- 胞子体不和合性 – 花粉の性質が花粉を生じた胞子体の遺伝子型によって発芽を阻止される場合で,胞子体に生じた物質が細胞質を通じて配偶体に影響 (キク科,アブラナ科など)
- 異型不和合性は異花柱花性 heterostyly がその典型的な例で,長・短 2 型のめしべとおしべの組合せをもつ植物 ( 例えばソバ,レンギョウなど ) と,長・中・短の 3 型の組合せをもつ植物 ( エゾミソハギやカタバミ属の種など ) などの場合がある。
腱 tendon
筋肉が骨につく部分をかたちづくる丈夫な組織で,緻密繊維性結合組織に属する。アキレス腱は最もよい例。
腱は一端が筋肉に移行し,他端は骨膜を通して骨実質内に侵入している。平行に走る密な膠原 ( こうげん ) 繊維の束とその間に存する腱細胞 tendon cell からなり,断面積 1 cm2について 500 kg の引張りに耐えることができる。
腱細胞は繊維芽細胞の一種で膠原繊維の間を縦にならんで,コウモリの翼のような形をなし,翼細胞とも呼ばれる。豊富な膠原繊維はこの腱細胞から生産されたものである。
1 本の腱は,その周囲を筋膜のつづきで,腱膜 aponeurosis と呼ばれる疎性結合組織の膜につつまれる。この疎性結合組織は腱の中に入りこみ,腱をいくつかの大まかな束にわけている。腱に出入りする血管や神経は,この疎性結合組織によって導かれる。
転写調節因子 transcription factor
遺伝子の転写を始めるために必要なタンパク質。いくつかの転写要因は,DNA の特異的な配列(< A HREF=”#Promoter”>プロモーター と エンハンサー )に結合する。また, 他のものは互いに結合したり,DNA に結合したりする。
[ 翻訳の調節 ]
屈性 tropism
植物の器官が外部刺激に呼応して一定の方向に屈曲運動する性質で,環境への適応現象の 1 つである。
刺激方向への屈曲を正の屈性,刺激源から遠ざかろうとする屈曲を負の屈性とよぶ。
屈曲運動は刺激源に面する側とその反対側での生長の差によっておこり,刺激の種類に応じて 屈光性 phototropism,屈地性 geotropism,屈熱性 thermotropism などに分けられる。
ベクター vector
組換えDNAを増幅・維持・導入させる核酸分子。 挿入するDNA断片の大きさや挿入の目的によって,それを挿入するために様々な特徴を付加された媒体がベクターとして使い分けられる。
また,単なるライブラリーをつくるためのベクターや,ひとまずクローニングするためのベクター,挿入したDNA断片からタンパク質を翻訳させる発現ベクターなどがある。
鋤鼻(じょび)器 vomeronasal organ
発見者ヤコプソン L. L. Jacobson ( 1783‐1843 ) にちなんで,ヤコプソン器官 Jacobson’s organ ともいう。
陸上四足動物の鼻腔の一部が左右にふくらんでできた臥状の嗅覚器官で,嗅球の後部内側の副嗅球からのびた鋤鼻神経に支配される。ふつうは盲嚢になっていて,両生類では鼻腔内へ,爬虫類と多くの哺乳類では鼻口蓋管を通じて口腔内に開く。
ヘビ,トカゲ類では涙管からの涙がヤコプソン器官へ流れ,内壁を湿らせる。カメ類では発達が悪く,ワニ類と鳥類では消失し,哺乳類のなかでも霊長類,コウモリ類,水生哺乳類では退化している。
ヘビ類とトカゲ類ではよく発達していて,鼻よりもむしろ主要な嗅覚器官になっている。これらの爬虫類が頻繁に舌を出し入れするのは,舌の先端に捕らえた空中のにおい物質を口腔内に開いたヤコプソン器官の開口部へ送りこんでいるのである。
哺乳類では鼻が主要な嗅覚器官となっていて,ヤコプソン器官は性フェロモンを感受するだけの器官となっている。
March 03, 2020