7.家畜の主な質的形質の遺伝
| このページの内容 |
7-1.毛色
哺乳動物における毛色は,被毛の蛋白質成分中にメラニン melanin を含有する色素がいかに沈着するかに依存している。
メラニンはチロシン tyrosine からチロシナーゼなどの酵素の作用によって産生され,ユウ(真正)メラニン eumelanin (暗色)とフェオメラニン phaeomelanin (明色)がある。
- ユウメラニンは茶色から黒色を示す色素である。
- フェオメラニンは明るい黄色から赤色にいたるまでの幅が見られる。
メラニンを生産する細胞は melanocyte と呼ばれ,産生された色素顆粒は eumelanosome または phaeomelanosome として知られる。
色素形成に関する遺伝的制御については未だ解明されていない点も多いが,現在では少なくとも6つの常染色体の複対立遺伝子座が色素の生産ならびに分布に影響すると考えられている。
必ずしも全ての対立遺伝子が知られている訳ではないが,多くの動物種で同様の遺伝様式が観察されている。
ほとんどの毛色の遺伝子座では2つ以上の対立遺伝子が存在するので,各遺伝子座はシリーズ series とよばれる。
6つの主要なシリーズ series(遺伝子座)の概要を示す。
| 1)Agouti (A) series アグーチ(A)シリーズ 野生色 |
agoutiとは野生のマウスやウサギの被毛に見られる’霜降り’(野生色)を表す。この名前は南アメリカのげっ歯類(モルモットに似た動物)に由来する。野生型の毛色で遺伝子Aは根元のほうが黒で毛端またはその付近に黄色のバンドが存在するものである。この遺伝子座の他の遺伝子により,被毛のバンドの幅が変化する。極端な場合は,すべてが黒色(黄色バンドが存在しないもの)または被毛全体が黄色が生じる。シェパードの鞍型斑紋やコリーの黒とタン(2色)のような身体全体の色素の分布に影響する対立遺伝子も知られている。 |
| 2)Brown (B) series ブラウン(B)シリーズ 褐色 |
この遺伝子座の遺伝子は色素顆粒の蛋白成分に関係があり,顆粒の形状に影響する。遺伝子Bは黒色の拡張した正常な顆粒を産生する。遺伝子bは遺伝子Bに対し劣性で,楕円または球状の顆粒を生産し,茶色またはチョコレート色(ウマの場合は栗毛)を示す。 |
| 3)Color Point (C) series 着色(C)シリーズ 着色因子 |
この遺伝子座はチロシン tyrosine をメラニン melanin に変換する酵素チロシナーゼ tyroninase の生成に関係すると考えられている。C遺伝子はチロシナーゼを正常に産生するので,正常な色素沈着が起こる。他の対立遺伝子は酵素の形成効率が悪く,結果的に色素顆粒が少なくなり,着色の程度が悪い。この遺伝子座には7つの対立遺伝子が確認されている。その中には,ビルマネコ(CbCb)とシャムネコ(CsCs) の特徴的なものが含まれている。これらの2つの遺伝子は温度感受性型のチロシナーゼを産生すると考えられている。すなわち,体の端は他の部位に比べ温度が低いので,チロシナーゼの作用は体の端に近いほど効果的となる。 |
| 4)Dilution (D) series 希釈(D)シリーズ 淡色化因子 |
この遺伝子座の遺伝子は顆粒の数を減少させるというのではなく,むしろ顆粒が塊を形成するのを抑制することによって,色素沈着の度合に影響する。D: 色素 の 希釈 なし( 野生型)d: 主にユーメラニン(黒~茶褐色)の色素を希釈するが,フェオメラニン(赤~黄褐色)も希釈される。色が薄められる対立遺伝子 d は常染色体劣性遺伝をする ため,dd という遺伝子型を持つ場合にのみ毛色は希釈されることになる。 |
| 5)Extention (E) series 拡張(E)シリーズ 黒色拡張因子 |
この遺伝子座の遺伝子は被毛個々の色素沈着と違って,身体全体の被毛の黄色と黒色の色素の程度に影響する。たとえば,遺伝子ebrは黒色と黄色の斑紋を生じさせ,イヌとウシで鞍型斑紋となる。 |
| 6)Pink-eyed dilution (P) series Pシリーズ 紅眼淡色化因子 |
対立遺伝子Pは黒色の色素顆粒にのみ影響し,その形状と構造に作用する。黄色メラニンには関与しない。この名前はこの遺伝子座の遺伝子の影響により,網膜における色素生産が全く行われないということに由来している。 |
| 7)その他の遺伝子座 | 特定の種で毛色や斑紋を決定するのに重要な遺伝子座が知られている。たとえば,猫では常染色体にあるTabby (ブチ猫)座位は3つの対立遺伝子を有し,abyssinian tabby (Ta), mackerel tabby (T), blotched tabby (tb)がある。 |
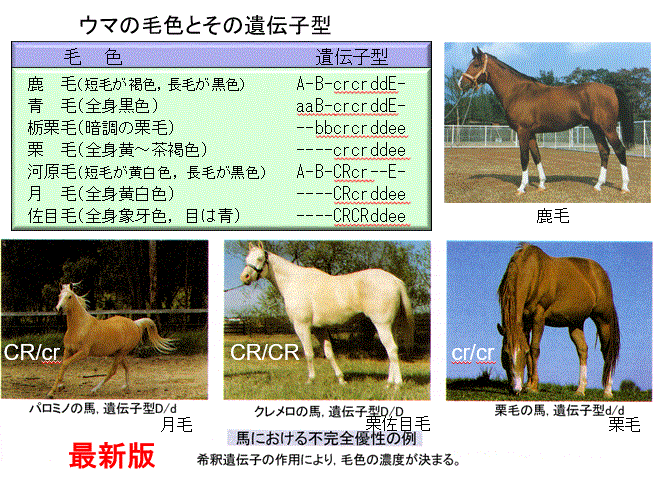
以下,具体的な毛色と羽色の例を示す。
ウシ:一般に黒色は褐色,赤色に対して優性で,褐色は赤色に対して優性である。
白色についてはシャロレイ種における白色は黒色に対して優性である。しかし,ショートホーン種の毛色の場合,褐色を支配する遺伝子と白色を支配する遺伝子とは無優性の関係にある。
ホルスタイン種,エアシャー種などの体各部に見られる白の斑紋は単色に対して劣勢である。
しかし,
- ヘレフォード種の顔面白斑
- ホルスタイン種の鼠径部白斑
- 白帯ギャロウエイの白色帯状斑
- ピンツガウ種の背線の白色線状斑
などは優性白斑である。
ブタ:ランドレース種,大ヨークシャー種,ヨークシャー種などの白色はすべて有色に対して優性である。
ニワトリ:黒色Eが褐色eに対して優性である。白色については優性白(白色レグホーン種)と劣勢白(白色ロック種)とがある。
優性白は抑制遺伝子Iに支配されており,色源体遺伝子の発現が抑制されるので白色となる。
一方,劣勢白の羽毛は白色遺伝子がホモになると羽毛のメラニン合成が阻害されるために発現する。 しかし,羽毛以外ではメラニンが産生されるので,眼は黒くアルビノとは異なる。
斑紋としては横斑プリマスロックなどに見られる横斑が代表的で,これは伴性の優性遺伝子Bに支配されている。
マウス:マウスに限らず齧歯類の場合には色源体遺伝子Cを欠くアルビノが普通に見られる。このアルビノ遺伝子cはCに対して劣性である。したがって,色源体遺伝子Cをもつものは有色となる。
7-2.外部形態
1)異常形質(家畜にみられる奇形の遺伝)
家畜の形態的特徴の遺伝については多数の報告があるが,その多くは奇形に関するものである。奇形の多くは致死または半致死であり,育種上の利用価値は殆どない。
| 異常形質 | その特徴 |
| ①致死遺伝子 (lethal gene) | ホモの状態で死亡する遺伝子[劣性致死遺伝子]をさす。優性致死遺伝子,つまりヘテロでも死に到らしめる遺伝子の存在も考えられるが,今のところ発見されていない。致死作用には劣性であるが,表現型としては優性のものも,劣性のものもある。 |
| ②半致死遺伝子 (semilethal gene) | 部分致死,不完全致死ともいう。完全致死遺伝子が胎生期に死に到らしめるのに対し,それほど強力ではなく繁殖年齢に達するまでに個体を死亡させる遺伝子をいう。多くは奇形を伴う。 |
2)正常形質
角性,肉髯と毛髯,冠,羽性の速さ,ならびに矮性などが知られている。遺伝子は大文字を優性,小文字を劣性とする。
| 正常形質 | その特徴 |
| ①角性 | ウシ:無角P,有角p ヤギ:無角H,有角h ヒツジ:従性遺伝の項でも述べたが,ヘテロでは♂有角,♀無角。 |
| ②肉髯 | ヤギの肉髯はスイス原産の品種にあって,英国種やアフリカのヌビアンにはない。有肉髯が優性。 |
| ③毛髯 | ヤギにみられ,従性遺伝する。毛髯がある方が雄で優性であるが,雌では劣性である。 |
| ④体型 | ウシには尻,腿の筋肉の発育が異常で,筋肉間に脂肪が少なく,臀溝を生じ,斜尻となることがある。これは豚尻 double muscle とよばれ,正常なものに対して単純劣性である。 |
| ⑤矮性 | 1遺伝子の作用で体重を著しく減ずる矮性 dwarf 遺伝子が種々の動物で知られている。 ウシ,マウスの矮性は正常発育のものに対して劣性である。一方,ニワトリにみられる矮性は伴性の劣性遺伝子に支配されている。 |
| ⑥冠型 | ニワトリにおける代表的な冠型として,クルミ冠,バラ冠,マメ冠および単冠の4種がある。 単冠が野生型で,無冠に対して優性である。マメ冠とバラ冠とはそれぞれ単冠を支配している遺伝子座とは別の遺伝子座の支配をうけていて,マメ冠遺伝子があればマメ冠に,バラ冠遺伝子があればバラ冠になる。 さらに,マメ冠遺伝子とバラ冠遺伝子の両方があると,それら両遺伝子の相互作用によりクルミ冠となる。 |
| ⑦遅羽性 | 遅羽性 slow feathering とは,たとえば横斑プリマスロックの雛において羽毛の生え揃うのが遅いことで,孵化後10日位の頃早羽性のものとの差が大きい。 これは伴性の複対立遺伝子Kn,Ks,Kおよびk+に支配されていて,前三者が羽毛の伸長を遅らせ,早羽性のk+に対し優性である。これを利用して雛の雌雄鑑別ができる。 |
7-3.血液型およびタンパク質多型
同一種の生物集団になんらかの形質について異なった2種類以上の個体が共存することを多型(文字どおり“多くの型”のこと)という。
ヒトの ABO 血液型の場合のように,多型的な形質が遺伝的なものである場合は遺伝的多型 genetic polymorphism という。
ヒトの血液型は,被検赤血球をヒトまたは動物からとった特異抗体(血液型判定用試薬)と混ぜたときに,凝集が起こるかどうかで決められる。ヒトでは,ABO,MN,Rhなどの多くの血液型が見いだされている。
ウシの血液型は通常,特異抗体による溶血の有無で判定され,ウマ,ブタなどの血液型の検査には凝集と溶血の両者が利用される。
| 多型のその他の例についてはこちら |
7-3-1.血液型
①定義ならびに分類の方法
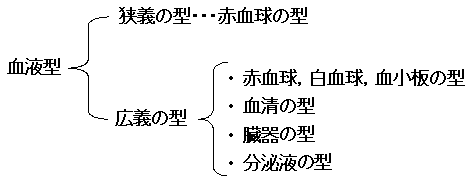 1901年にランドシュタイナー Landsteiner がヒトの赤血球に個体変異を見いだし,それを 血液型 blood group と呼んで以来,血液型といえば赤血球の型を意味するのが普通であった。
1901年にランドシュタイナー Landsteiner がヒトの赤血球に個体変異を見いだし,それを 血液型 blood group と呼んで以来,血液型といえば赤血球の型を意味するのが普通であった。
しかしその後,白血球,血小板あるいは血清,臓器,分泌液にも,抗原抗体反応や電気泳動胞などの方法で種々の変異が見いだされるようになり,それらを総称して血液型と定義されるようになった(図)。
(狭義の)血液型は赤血球の細胞膜の抗原性の違いによって分類される。たとえば,A型と判定されたヒトの赤血球表面にはA型抗原が,B型と判定されたヒトのそれにはB型抗原が存在することを示している。
血液型抗原は,いずれも単純なメンデル遺伝をするので,遺伝標識として遺伝学の研究や親子の鑑別によく利用され,型の出現頻度に人種差・民族差があるので,人類学の研究にも欠かせないものとされてきた。
血液型抗原の産生は,すべて遺伝子に支配されるが,数ある血液型抗原のなかには遺伝学的に互いに密接な関係をもっているものがあり,それによってこれらの抗原をいくつかの系に分けることができる。
たとえば M と N の2種の抗原をしらべてみると,M 抗原のない(-,陰性)人は N 抗原をもち(+,陽性),逆に N 陰性の人はM 陽性であり,両抗原の間に対立関係があることがわかる。
これは M 抗原と N 抗原の産生を支配する遺伝子が同じ染色体の同じ場所(座)を占めているからで,M と N とは一つのグループとして扱われる。このようなグループを 血液型システム (あるいは単にシステム)といい,MN 血液型システムあるいは MN 血液型というように呼ばれる。
一つのシステムのなかで,たとえば M 抗原をもち N 抗原をもたないものを M 型,その逆を N 型,両抗原をもつものを MN 型というふうに二つ以上の型(表現型)を区別することができる。
家畜の血液型はさらに複雑である。
たとえば,ウシの赤血球抗原には,A,B,C,・・・・・ 等多数の抗原が見いだされており,そのうちB,G,およびKと名付けられた3つの抗原は単独で検出される場合もあるが,多くはBGKとして一緒に検出され,同一の遺伝子によって支配されていることが明らかにされた。
そこで,これまでB,G,Kのそれぞれを抗原と呼んでいたのを改めて血液型因子(blood factorまたはantigenic factor)とよび,1つの遺伝子によって決定されるBGKのような複合抗原をフェノグループ(phenogroup)または単に抗原と呼ぶようになった。
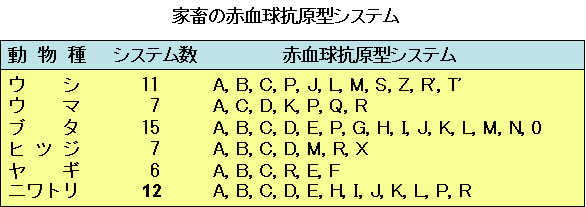
| まとめ |
| 血液型を支配する遺伝子座は1つではなく,かなり多数存在することはヒトを初め多くの家畜で見いだされている。同一の遺伝子座に属する対立遺伝子によって決定される血液型は 血液型システム (または単にシステム)とよばれる。たとえば,さきのウシのB,G,Kの各因子はBシステムに属する遺伝子によって決定される。血液型遺伝子の記号は,遺伝子座すなわちシステムを表わす記号の右肩にフェノグループを示して表わすのが一般的である。BGKの例ではBBGKと書く。 |
②家畜の血液型とその特徴
家畜の血液型システムの大部分は複対立遺伝子よりなっており,また遺伝子数が非常に多い。そのもっとも極端な例は牛のBシステムである。
7-3-2.白血球型と組織適合性
最近医学の分野において,皮膚または臓器の移植がよく行われるようになってきたが,その成否を左右しているのが組織適合性抗原 histocompatibility antigen である。
組織適合性抗原はまた移植抗原ともよばれ,宿主と移植片の移植抗原の組合せが適合していれば移植片は永久に生着するが,不適合であれば脱落する。
移植抗原は白血球抗原と密接に関連しているので,多くの動物で白血球抗原の探索が行われている。なお,一部の動物では,血液型抗原が主要な移植抗原となっている例も知られている。
7-3-3.タンパク質多型
デンプンゲルを支持媒体とする電気泳動法が開発されて以来,血液,乳汁,またはその他の体液に含まれる蛋白質の遺伝的変異の検出が容易になった。現在では,この種の研究は免疫遺伝学とともに,家畜育種の重要な分野となっている。
①変異の検出法
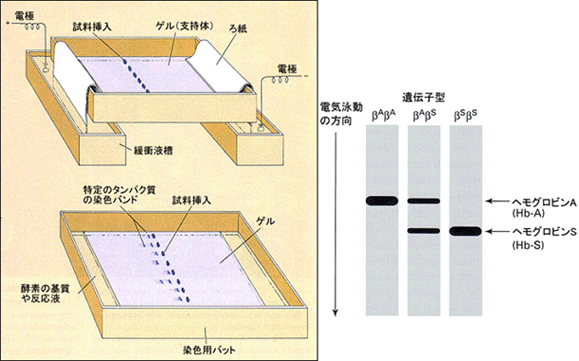 タンパク質の個体変異の検出には,主としてデンプン,ポリアクリルアミドまたは寒天ゲルなどを支持媒質とするゾーン電気泳動法が用いられる。
タンパク質の個体変異の検出には,主としてデンプン,ポリアクリルアミドまたは寒天ゲルなどを支持媒質とするゾーン電気泳動法が用いられる。
この方法は蛋白質の荷電の差異のほかに,ゲルの微細構造による分子篩的効果が加わり,蛋白質の分離に優れた性能を示す。
酵素の場合は,それぞれ目的の酵素によって特異的に分解される基質を反応させ,生じた物質をアゾ色素などによって発色させて検出する。
同じ基質特異性(ある特定の物質のみを分解あるいは合成する性質)を示すが,異なった分子構造(アミノ酸配列)を持つ酵素タンパク群をアイソザイム isozyme という。
②家畜における主要な変異
血液,乳汁,卵白を初めとして,種々の体液または臓器の抽出液などについて電気泳動することにより,蛋白質の遺伝的変異は多数検出されている。これらの変異のうち,とくに血清タンパク質で検出された変異の数を表に示す。
<畜産における血液型の応用>
家畜は経済動物であるため,輸血の必要の起こるような場合には処分されることが多い。
①親子鑑別 【個体レベル】
人工授精の結果,真の父親が不明な場合がしばしば生ずる。このような場合,親と子の血液型を調べることによって,かなりの精度で親子の判定を行うことができる。なお,親子鑑別には血液型のほかに,血清タンパク質の多型も併用されるのが普通である。
②フリーマーチンの判定 【個体レベル】
ウシの異性双子のメスのおよそ90%はフリーマーチンとして繁殖不能となる。胎生時の双子の血管吻合によって相互に赤血球の原基細胞が交換されると,血液型は同じとなる(赤血球キメラ) 。そこで,異性双子分娩の時には生後なるべく早くこのメスが正常であるか否かを知るために,血液型を検査する。
③疾病(血液型不適合)の回避 【個体レベル】
母と子の血液型の不適合によって生じるヒトの場合のRh血液型と同じようなものとして,豚ならびに馬の初生子黄疸症がある。
④品種構造の分析 【集団レベル】
これは多型遺伝子を利用して,品種の遺伝的特徴を分析し,それにより他品種との類縁関係またはその品種の成立過程などを調べる方法である。
⑤量的形質(経済形質)との関連性 【集団レベル】
血液型または蛋白質多型と量的形質との関連性については非常に多くの研究が行われているが,現在までにかなりはっきりしたデータが得られているのは鶏の血液型のBシステムと牛の血清トランスフェリン(Tf)型である。
ニワトリのBシステムでは,一般にヘテロ接合体になると,生存率,孵化率などの適応度に密接に関連した形質がホモのものより優れてくる傾向が認められている。
ウシのTf型では,TfD遺伝子はTfAまたはTfEに比べて乳量を増加させる傾向が認められ,ホモ×ホモの交配はヘテロとの交配よりも一般に受胎率が高いといわれている。乳脂率とBシステムとの関係もあるらしい。
これは第一に血液型と経済形質に関する遺伝子が同一でその多面作用による場合,第二に関係遺伝子が同一染色体上にあり連鎖関係にある場合,第三に血液型から窺われるヘテロ性に好影響を及ぼす場合などが考えられる。
7-4.質的形質と量的形質の関係
質的形質の遺伝様式は比較的単純な遺伝子支配を受けているが,量的形質に関しては複雑である。
したがって,質的形質と量的形質の間に強い遺伝相関があるなら,質的形質を取り上げて,量的形質の改良を図ることができ有用である。しかし,これまでのところ,高い関連性を示す形質はあまり見いだされていない。
〔研究例〕
○鶏の血液型のBシステムと生存率,孵化率
○鶏の冠型のバラ冠遺伝子と受精率
○乳牛の血清TfD遺伝子はTfAまたはTfEに比べて乳量を増加させる傾向
○豚の血液型およびアイソザイムには肉質と関連しているものがある。
7-5.DNA多型
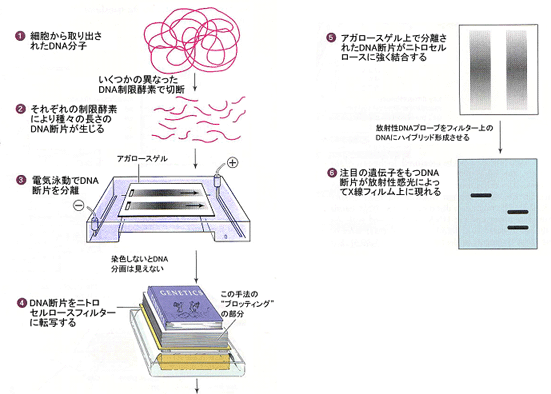 生物において,さまざまなレベルで検出される遺伝的変異も,究極的にはDNA分子の塩基配列レベルでの変異として捉えることができる。これをDNA多型 DNA polymorphism という。
生物において,さまざまなレベルで検出される遺伝的変異も,究極的にはDNA分子の塩基配列レベルでの変異として捉えることができる。これをDNA多型 DNA polymorphism という。
7-5-1.制限酵素段片長多型
制限酵素 restriction endonuclease は二本鎖DNAの特定の塩基配列を認識し,切断する酵素である。これを用いて切断したDNA断片をアガロース電気泳動にかけると,長さの異なる断片がそれらの移動度の差から分離してくる。ゲル中の特定のDNA断片を検出するのにサザンブロット Southern blot と呼ばれる方法が用いられる。
このように特定の制限酵素によるDNA断片の長さの差が移動度の違いとして検出されるDNAの多型を制限酵素断片長多型 restriction fragment length polymorphism, RFLP という。
| RFLPの詳細についてはこちら |
| RFLPのその他の例についてはこちら |
7-5-2.VNTRs(variable number of tandem repeats)
哺乳動物のゲノムにはミニサテライトと呼ばれる数塩基から数十塩基を単位とする配列が数十回繰り返した直列の反復配列が数多く存在する。この領域を含む制限酵素断片を特定のDNAプローブを用いてサザンブロットを行うことにより多型が検出される。
これはミニサテライトの反復数の違いであり,RFLPの一種であるが,その生じる原因が異なることや非常に多型性に富んでおりヘテロ接合体になることが多いことからRFLPと区別してVNTRsと呼ばれる。
7-5-3.DNAフィンガープリント
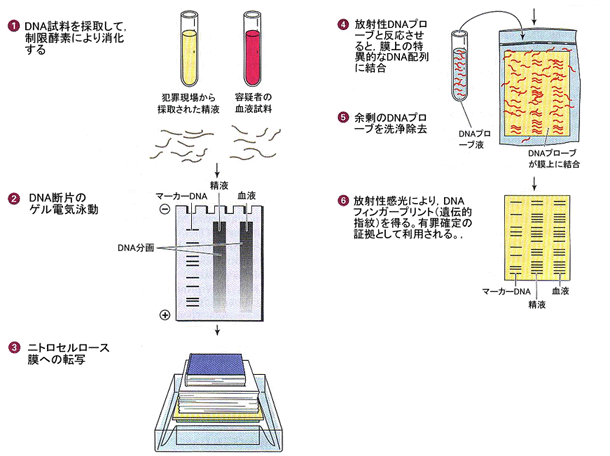 DNAの特定の部分におけるミニサテライトの反復配列数の多型をVNTRと呼ぶのに対して,同じミニサテライトの反復配列がゲノムの任意の場所に散在している場合がある。
DNAの特定の部分におけるミニサテライトの反復配列数の多型をVNTRと呼ぶのに対して,同じミニサテライトの反復配列がゲノムの任意の場所に散在している場合がある。
これら散在性反復配列における反復数は10~1,000回にものぼり,その数が場所により異なるので,制限酵素で切断した後共通配列のミニサテライトをプローブとしてサザンブロットを行えば数多くのバンドからなる複雑な泳動パターンが得られる。この泳動パターンはジェフレイ (Jeffrey, A.J., 1985) によりDNAフィンガープリント (DNA fingerprint) と名付けられた。
VNTRやDNAフィンガープリントは,従来鼻紋,斑紋,血液型などにより行われてきた個体識別,親子鑑別,双子の卵性診断などに利用される。
7-5-4.マイクロサテライト
DNAの塩基配列の中にCA(GT)などの短い配列が数回から十数回反復している部分があり,これをマイクロサテライト (microsatellite) と呼ぶ。
この反復回数には個体変異が非常に多く,しかも1本の毛髪などのサンプルを用いてその変異型の判定ができることが明らかになった (Higuchiら,1988) 。
このDNA多型はヒトや家畜の遺伝病の遺伝子診断をはじめ,遺伝子マーカーとしての広範な利用が期待され,近年活発に研究が行われている。
| 最初に戻る |
| メニューのページへ戻る |
February 03, 2020