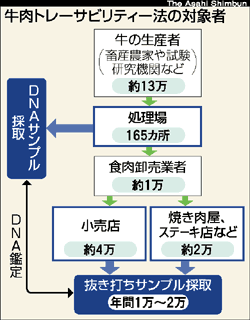国産牛、DNAで身元保証 年125万頭の肉片保存
2004年08月28日
国内で食肉用に処理されるすべての牛のDNAを採取し、偽装表示などを防ぐ鑑定用のサンプルとして保存する作業が12月から始まる。小売店や焼き肉屋、ステーキ店などで流通する牛肉についても、12月から品種や生年月日などの個体情報を記録した識別番号を表示するようになるが、保存しているサンプルと比較すれば、商品の表示と中身が一致しているかどうかが、正確に確認できる。輸入品以外のすべての牛肉の「身元」は保証されることになる。牛海綿状脳症(BSE)の発生や相次ぐ偽装表示で失った消費者の信頼を回復することがねらいだ。
牛肉トレーサビリティー法に基づく調査。国内165カ所の処理場で牛肉に処理される年間約125万頭すべてから小豆大の肉を採取し、DNA情報のサンプルとして3年間保存する。農水省は、年間に1万~2万点の牛肉を小売店などで抜き出し、DNA鑑定して表示された肉と同じものかどうかを調べる。
すでに、牛肉の偽装表示を防ぐため、高価な「和牛」と品種表示されている牛肉の一部に対しては、DNA鑑定を実施している。これに対し、新たに始める調査は国内で牛肉に処理されたすべての牛が対象だ。
牛肉トレーサビリティー法では、品種、生年月日、生育地、処理の年月日などの個体情報を記録した識別番号を表示することが義務づけられている。今回の新たな調査で識別番号が本当かどうかが正確に確認できるようになる。
食肉は流通過程が複雑なため、生きた牛を処理した後で販売用に小さく切り分けたり、小売り用にパック詰めしたりする際に別な肉が混入し、表示と中身が異なってしまう可能性が指摘されていた。
これに対し、農水省は「すべての牛肉のDNAの採取・保存と店頭での抜き打ち採取を組み合わせることで、故意の偽装表示だけでなく過失による表示ミスも防ぐことができる」(消費・安全局)としている。また、後を絶たない偽装表示に対する大きな予防対策にもなるのは確実だ。
ただ、調査するのは、牛肉トレーサビリティー法で個体識別番号の表示が義務づけられた国内で処理された牛肉。市場の約6割を占める輸入牛肉は含まれない。農水省の狙い通りに、消費者の牛肉に対する信頼を回復する決め手となるかどうかは不透明だ。
〈牛肉トレーサビリティー法〉 03年12月に施行された「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」の通称。01年9月に国内初のBSE感染牛が確認されたのをきっかけに、国産牛の安全性を確保する狙いで制定された。国産の牛に出生段階で10けたの個体識別番号をつけ、生育情報などの記録を義務づけた。今年12月からは牛肉の流通業者、小売り・外食店も識別番号を表示する義務を負う。違反した場合は、農水相が改善を勧告・命令する。悪質な場合は、30万円以下の罰金が科される。
(04/08/28 22:44)
《朝日新聞社asahi.com 2004年08月28日より引用》