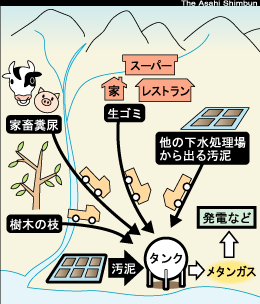生ごみ、家畜糞尿など集め発電 国交省、事業推進へ
2003年08月25日
生ごみや家畜の糞尿(ふんにょう)、木くずなどのバイオマスを下水処理場に集め、下水汚泥とともにエネルギー資源として活用する事業の推進に国土交通省が乗り出す。密閉タンク内でメタンを含むバイオガスを発生させ、発電や暖房に利用する。今月中に自治体に参加を呼びかけ、数年以内には事業に着手したい考えだ。下水汚泥や糞尿を使った発電は実用化されているが、1カ所にまとめて活用する試みは初めて。
バイオガスを発電に利用している下水処理場は横浜市や大阪市などに19カ所。しかし、単独ではガスの発生量が少なく、コストに見合わないことが多いため、燃やして処分する処理場もある。
そこで、拠点となる処理場を決め、近隣の下水処理場や農村部の集落排水施設から出る汚泥をトラックで運び、活用することにした。生ごみや家畜糞尿、木くずなども集めて一緒に発酵させる。出てきたガスを発電に利用、余熱を暖房に使う方法が有力視されている。
試算では、流域が十数万人程度の処理場から出る汚泥を単独で使った場合、処理場で使う電力の3割しか自給できないが、近隣の汚泥をまとめて使うと電力自給が6割程度に上がる。生ごみや木くずも利用すれば100%の自給も可能という。
同省では、発酵タンクや発電施設の建設費の半額程度を補助する新しい事業を今年度から新たに設けた。発酵タンクを一般廃棄物処理施設として登録するなど様々な手続きが必要で、計画立案や事業の進め方をまとめた手引書を作る予定だ。
<バイオマス>
生物に由来した有機物のこと。木くずや建設廃材、間伐材などの木質系廃材、下水汚泥、家畜の糞尿、食品廃棄物などがある。燃やして使っても、発生する二酸化炭素は植物が大気から取り込んだものなので、温室効果ガスの削減量を定めた京都議定書でも排出量にカウントされない。
(08/24 09:37)
《朝日新聞社asahi.com 2003年08月25日より引用》